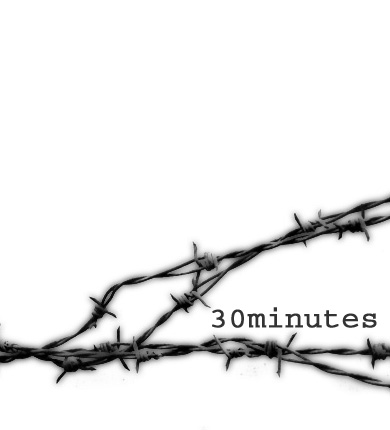「一護サン,何飲む…?」 テーブルに頬杖をついた浦原が欠伸を噛み殺すような顔でメニュを寄越したのを受け取った一護は,そこに並んだ文字を見つめて呆然とした。 コーヒー,1400円,カフェオレ,1600円,オレンジジュース1200円…。 とてもじゃないが一護の常識の範疇を超えた値段設定だった。 浦原は横を向いてくあああ,と欠伸を漏らし,一護が戸惑いを浮かべた顔で自分を見ていることに気づくと唇だけで「好きなもの,ドーゾ」と云った。 好きなもの,て云ったって。 メニュを上から下まで睨み付けるように見つめて,ようやく見つけたのが「ペリエ700円」の文字。 ペリエってなんだ? でもまぁ飲み物なんだろう。 そんな風に思い切って「俺,ペリエ」と呟くようにで云った。 そんなんでいいの?と目顔で問うてくる浦原に頷くと浦原はくすりと笑ってウェイトレスに向かって口を開いた。 「ブレンドとペリエ,ひとつずつ」 「かしこまりました」 感じのいい笑顔を浮かべて小さく一礼したウェイトレスがテーブルから離れると,一護はテーブルに向かって身を乗り出した。 「なんだよこの値段!」 「ええー,ホテルなんてみんなこんなものじゃんかないんスか?」 「ふざけんなよ!コーヒー1400円て!普通の店なら三杯飲めるぞ!」 「普通,ねぇ。でもま,ここ味はそこそこなんで」 「……理解できねぇ」 一護は諦めたように息を吐き,椅子に背を凭れさせた。 平日の午後のホテルのティ・ルーム。 辺りにいるのは商談だろうか。堅苦しいスーツに身を包んだ会社員風の男性たちと,やけに派手な身なりの中年女性,それに外国人などで,自分のような若い,しかもジーンズ姿の人間なんてひとりもいなかった。 浦原にしたって今日はいつもの羽織に作務衣に下駄ではなく,チャコールグレイのスーツに身を包んでいた。 ため息が出る。 なんでついてくる,なんて云っちまったんだろう。 くしゃくしゃと髪をやりながら小さくため息を吐くと,テーブルに頬杖をついた浦原が一護の名を呼んだ。 「いーちご,サン」 「…ンだよ」 「居心地,悪い?」 「わかってんなら聞くなよ」 「あはは。でもアタシは楽しいっスよ?」 「あ?」 「一護サンの普段は見られない顔,見られるし」 困ってる一護サンなんてほら,そうそう見られるものじゃないでしょ? ふわり,口の端に浮かぶ微笑はやわらかなもので,一護は一瞬目を奪われてしまう。 すぐに目をそらして,バツの悪さをごまかすように「悪趣味」と低い声で罵ると,ウェイターが「お待たせしました」とテーブルの横に立った。 「こちら,ブレンドコーヒーとペリエになります」 やわらかな声で云いながら,カップをかちゃりとも言わせずにテーブルに置く。 この辺がホテルのサービス,というヤツなんだろうか,と思いながら一護はその様子を見ていた。 「でも一護サン,よかったの?」 浦原の声に顔を上げると,視線で傍らのグラスを示された。 そこにあったのは氷の満たされたグラスと緑色の壜。 グラスの縁には櫛形に切られたライムが添えてある。 「外,寒いから避難してきたのに」 「…るっせぇな。ここん中は暖かいからこれでいいんだよ」 何もかもを見透かしたような浦原の物言いに一護は不貞腐れ顔でそう返しながら壜の蓋を開けてペリエをグラスに注いだ。 しゅわしゅわしゅわ,と泡の弾ける微かな音を聴きながら確かに冬の飲み物じゃねぇなこれ,とひとりごちる。 添えられていたストローに手を伸ばしかけてグラスの縁に添えられたライムが気になった。 ここにこれがある,ということは絞っていれろ,ってことなのか? 三秒ほどじっと見つめた後,一護はおもむろにセータの袖をまくるとライムを摘んでグラスの上でぎゅ,と絞った。 しかし小振りのライムは一筋縄ではいかず,グラスに零れる量よりも多くが一護の掌から手首に向けて飛んでしまう。 「げ」 一護が苦々しげに呟いてテーブルの端に置かれた紙ナフキンに手を伸ばすと,それが届くより先に浦原にその手を攫われた。 「…!」 一護が制止する間もなく浦原は一護の手首を伝う果汁に唇を寄せた。 ちゅ,と音を立てて雫を吸うとあまりの出来事に目を見開いている一護の視線を捉えたまま手首に向かって舌を這わせる。 浦原の視線の先,一護の顔がくしゃりと歪んだ。 「ねぇ一護サン。せっかくだから,部屋,寄っていく?」 あんまり反応可愛いから,我慢できなくなっちゃった。 冗談めかして云う言葉に含まれた本気を耳が掬い取り,一護は皮膚が粟立つのを感じていた。 俯いた視線の先,一護の手から零れ落ちたライムが炭酸水の中,ゆっくりと沈んでいく。 手首が熱い。 この熱を冷まさないと,早く冷まさないと,自分は――。 けれども一護は動くことができなかった。 周囲の音は遠のき,場違いだとか居心地が悪いだとかそんな気持ちも吹き飛んだ。 そんな一護を見つめていた浦原は,くすりと笑うと「それ,飲み終わるまでに答えちょうだい?」と甘く誘う声でささやく。 一護は開放された手の熱を一瞬でも早く冷まそうとグラスを掴んだ。 うすいうすいグラスの縁を伝って冷たく仄甘い炭酸水が流れ込む。 喉を伝うその冷たい感触が熱を自覚させる。 ちきしょう。 一護は声に出さずに呟くと,グラスの氷をひとつ,がりり,と噛み砕いた。 ------------------------ タイトルはアレです。 書き上げるまでにかかった時間。 受時々小悪魔なあのひとからのメィルに条件反射で食いついたシロモノ。 赤坂,ペリエ,ライム。から連想。 送り返したメィルの頭にはそんな文句がついておりました。 (ページレイアウトだけは誇るよ!好きな感じにできました…v) (2007.02.26) |