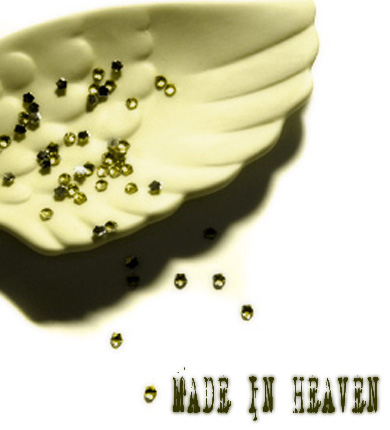不機嫌な顔をした神様に会った。 不機嫌も不機嫌。 それはそれは凄まじい仏頂面。 空を渡る風に白いシャツが翻って細い身体が覗く。 よく見れば首も,肩も,腕も,どこもかしこも細い。 その細い身体でこの世界を支える,唯一無比のひと。 神様は下界が見下ろせる崖の端に無造作に座って片方の膝を抱いていた。 視線は下界に。 口をぎゅっと引き結んで睨み付けるように。 何がそんなに彼を苛立たせるのか気になって同じように下界を見下ろしてみる。 しかしそこにはいつもとなんら変わらない混沌とした世界が広がるだけだった。 「何覗き見してんだよ」 ありゃ,気づかれちゃった。 気配を殺すことをしなかったのはまぁわざとだったから,へらりと笑って姿を見せてみる。 「どーも,コンニチハ」 「仕事サボってんじゃねぇぞ,天使」 「神様こそ。なんでこんなところで仏頂面?」 「……うるせ,不機嫌面は生まれつきなんだよ」 ぷい,とそっぽを向いた神様はその名にふさわしくないほど子供じみて見えた。 崖の下から風が吹いてくる。 伸ばしっぱなしの髪が嬲られて舞い上がるのを感じながら神様を見た。 神様はこの世界で唯一の色を持つ。 その鮮やかな橙色の髪が,やわらかそうにそよいでいるのを見てつい,魔が差した。 気がついたら手が伸びていて。 気がついたら髪を梳いていた。 「……テメェ,なんのつもりだ」 ジロリ,斬りつけられるような視線にさらされて苦笑い。 すぐに手を引こうとは思ったのだけど,あまりにもその手触りが心地よくて,目顔でもう少しだけ,と希ってみれば,ふい,と視線が逸らされた。 神は願いを叶える者。 だからアタシ風情のこんな不埒な願いでも叶えないわけにはいかない。 卑怯だったかな,と思いながらも,せめてこの華奢な神様の悲しみが少しでも和らぐようにとやさしくやさしく髪を梳いた。 悲しみが,和らぐように? 何の気なしに頭を過ぎった思いに,先ほどの違和感の正体を知った。 そうか,アレは不機嫌なんかじゃない。 悲しんでいたんだ。 「ねぇ神様」 「なんだよ」 そっぽを向いたままぶっきらぼうに答える神様の肩の辺りを見ながら言葉を継いだ。 「どうして,そんなに悲しそうな顔してるの」 視線の先の細い肩が揺れた。 神様は抱えた膝を抱く腕にぎゅ,と力を込めて俯いてしまった。 指の間から鮮やかでやわらかな手触りの髪がすり抜けていき,アタシまでもが寂しくなる。 「神様?」 呼びかけて,手を伸ばす。 けれども触れてはいけないような気がして,伸ばしかけた手を引っ込めた。 「なんで俺の手は二本しかないんだろう,て考えてたんだ」 優しい優しい神様。 地上で涙を零す人間たちの悲しみを共有し,その胸を痛めている。 馬鹿なひと。 そう思わずにはいられない。 そんな風に心を痛めたってどうにもならないことは無数にある。 いちいち傷ついていたら,いつかその心は砕けてしまう。 そのことがわからないわけでもないだろうに。 気がつくと引っ込めた手をぎゅっと握り締めていた。 掌に爪が食い込むほど,ぎゅっと。 「…千手観音にでもなりたかった?」 「センジュカンノン?」 なんだそれ。 そんな風に見上げてくるまっすぐな神様の目を見つめてアタシはいい加減な説明をする。 「仏教のヒトですよ。千本もの手を駆使して衆生の民を救う,てのがコンセプトの」 「千本,か」 きれいな瞳に浮かぶ光が,また翳ってしまった。 自分の無力さを責めているんだろう。 不意に昔読んだ物語を思い出した。 金や銀や宝石で飾られた王子の像の話。 ――「ずっと向こうの」と王子の像は低く調子のよい声で続けました。 「ずっと向こうの小さな通りに貧しい家がある。窓が一つ開いていて,テーブルについたご婦人が見える。顔はやせこけ,疲れている。彼女の手は荒れ,縫い針で傷ついて赤くなっている。彼女はお針子をしているのだ。その婦人はトケイソウの花をサテンのガウンに刺繍しようとしている。そのガウンは女王様の一番可愛い侍女のためのもので,次の舞踏会に着ることになっているのだ。その部屋の隅のベッドでは,幼い息子が病のために横になっている。熱があって,オレンジが食べたいと言っている。母親が与えられるものは川の水だけなので,その子は泣いている。ツバメさん,ツバメさん,小さなツバメさん。私の剣のつかからルビーを取り出して,あの婦人にあげてくれないか。両足がこの台座に固定されているから,私は行けないのだ」 王子は柄のルビーがなくなるとサファイアでできた両の瞳を,瞳がなくなると全身を覆う金箔を剥がしてツバメに持たせた。 みすぼらしくなった王子は打ち倒されて溶鉱炉に放り込まれる。 最後の場面は童話らしくもっともらしい救いが設けられていたけれど,アタシはそれが嫌いだった。 心優しい王子も嫌いだし,ツバメも嫌い。オマケに作者もクソクラエだと思った。 その話に出てくる王子に,神様の横顔が重なった。 胸の奥にちり,と苛立ちが点る。アタシは少し意地悪な気持ちで神様を見つめた。 「でも,たとえ手が千本あったとしても,千一人目はその手から零れ落ちてしまう。そのひとのことはどうするの」 「……ッ」 「この世界に完全なものなど存在しない。唯一無比の存在であるアナタですらそうなのに。それ以上何を望むの」 アタシの言葉に,神様の顔がくしゃりと歪んだ。 今にも泣き出しそうな,つらそうな,つらそうな顔。 「ンなこと云ったって,見えるんだよ。泣いてたり,泣くことすらできなかったり。そういうヤツらが見えてんのに,俺には直接手を差し伸べることはできない。代わりに手足になって動くはずのオマエらにしたって基本的にサラリーマンで必要最低限しか仕事をしない。たまに熱心にやってるように見えるヤツがいるかと思いきや階級上げることしか考えてねぇで,評価の対象にならない仕事は見て見ぬフリだ」 神様はやるせなさを吐き出すようにそう云った。 「つーか,そんなに階級上がりてぇの?こんな無力な存在でも『神』になりてぇの?」 「……どうなんでしょ。アタシは基本的に出世とか興味ナイんで」 「つーかオマエ所属どこだよ。羽隠してんなよ。見せてみろ」 じっと見つめられ,逃げられなくなる。 仕方なしにアタシは首をこきりと鳴らすと隠していた羽を露にした。 神様はアタシの肩越しに現れた羽をじっと見つめて「あ,テメェ!」と顔を険しくした。 「十二宮のボンクラ熾天使じゃねぇかッ!」 「ボンクラって酷い」 「仕事サボリまくってるって報告来てんだよ!名前は…確かアレだ。浦原ッ!」 悪名轟く,てのはこういうことを云うんスかねぇ。 背中の三対の羽をばさりと揺らして頬をぽりぽり掻くと髪の手がにゅっと伸びてきて頭をごちんと叩かれた。 「痛ッ!」 「天誅!」 そりゃ,相手は神様だからまさしく天誅だけど,普通云います,そんなこと。 思わずくすくす笑いが毀れて,アタシは再び神様の横に腰を下ろした。 「神様,よくアタシの名前なんかご存知でしたね」 「…オマエだけじゃねぇよ。全員覚えてる」 「へぇ,そりゃ凄い。アタシなんて未だに部下の十分の一も…」 「覚えてねぇのか,オマエ」 神様は怒った顔というよりも,呆れたような情けない顔でアタシを見た。 神様のくせになんて表情がよく変わる。 けれどもそれは不思議なことに好もしくアタシには感じられて。 「もうちょっと早く知ってればな」 「?」 「アナタのこと」 「は?」 きょとんとした神様に,アタシは笑ってみせる。 「仕事の意義がわかんなかったんスよ。アタシは神様と違ってちっとも優しくないもんで,ヒトが泣こうが喚こうがなんとも思わない。でも仕事だからこの手を差し伸べる。頭使って部下動かしてそうして救ったところで,ヒトはまた同じ過ちを繰り返す。そんな仕事になんの意味があるのかなって」 「…浦原」 神様は痛いのを堪えるような顔をする。 全てを知ったその上でも救いたいと希う。 それは神の特性だから。でも,それだけでは言い表せない想いがそこにあるようにアタシには思えた。 だから,アタシは神様に向かって「でも」と言葉を継いだ。 「でも,アナタには違うモノが見えてるみたいだ。だったらアタシはアナタに従う。アナタのことを信じようと思う。ねぇ神様」 立てた膝に顎を乗せて,悪戯ににぃ,と口の端を引き上げると,こちらを向いた神様の頬がちょっと赤くなった。 「アタシがいっしょうけんめに働いたら,ご褒美くれます?」 「…ご褒美だァ?」 ……神様,柄が悪い。 跳ね上がった語尾にくすりと笑って,神様に手を伸ばす。 触れた髪はやっぱり心地がよくて,何度も,何度も触りたくなる。 「給料貰ってんだろ」 「アレはほら,必要最低限。あのね,云っとくけどアタシ能力高いっスよ?鼻歌混じりの片手間でここまで昇ってこれる程度には」 「傲慢な物言いだな」 「嘘は云ってないっスよ」 きっぱり言い切ったアタシに,神様は尚も胡散臭そうな目を向ける。 でも,胡散臭そうな目を向けてきながらも,「で,何が望みだ?」と聞いてくれる。 「名前教えて」 「は?」 「神様はアタシたち天使の名前を全員覚えてるんでしょ」 「あ,あぁ」 「でもアタシは神様を『神様』としか知らない。みんな知らない。だからアタシはアタシだけの『特別』が欲しい。それがご褒美」 神様はアタシの言葉をじっと考えているようだった。 みるみるうちに眉間の皺が深くなり,視線が逸れて,周囲からは音が引いた。 アタシは両手を後ろについて馬鹿みたいに青い空を見上げて神様が答えを出すのを待っていた。 「…黒崎,一護」 「え?」 「名前,知りてんだろ?それが俺の名前」 びっくりして神様を見ると,神様は眉間に皺を寄せたまま「オマエ,変なヤツだな」と笑った。 その笑顔は今日目にした中でいちばんの,アタシが好きな顔だった。 「黒崎サン。一護サン。一護サン,て呼んでいい?」 「……人前では呼ぶなよ」 「はぁい」 アタシは上機嫌で返事をすると,服についた埃を払って立ち上がった。 「さて,そしたら仕事してきましょっかね」 「…しっかりやれよ」 「えぇ。がんばってがんばって,次のご褒美貰わないと」 「え,なんだそれ!」 アタシは地面をとん,と蹴って下界に向けて飛び降りた。 背中に神様の…一護サンの「オマエ,そんなの聞いてねぇぞ!」と怒った声が降ってきたけど,そんなの構うものかと思った。 一護サンはやさしい。 あのひとの顔が曇らないように,この手を,この身を使ってアタシは働く。 アタシはツバメにはならない。 あのひとを幸福の王子になんてさせない。 あのひとを,アタシが幸せにする。 「次のご褒美は何をねだりましょっかねぇ…」 くすりと笑って呟くとそこはもう下界だった。 アタシは眩しい太陽の光を手で遮って空を見上げる。 青い空。 さっき見たのと同じ,真っ青に晴れた空。 でも違う。今見上げるこの空にはあのひとがいる。 ------------------------ 寝ぼっけの頭にふわりと浮かんだのはこんな話。 ……浦原さんにね,羽生やしたかったんです。それだけ。(脱兎) 「幸福の王子」は「青空文庫」から引用しました。 (2007.01.30) |